����E�Ӗ��
����h�q�ǂ̍H�����s��
�m������ƒ�~���w��
�R���Q�R���A�����Y�u���ꌧ�m���́A����s�Ӗ�Â̐V��n���݂̊C��ł̈�@�ȍH���ɒ��~�̎w�����o�����B����h�q�ǂ��A���ߗ��Ēn���u�C�]�[����������̈�ŁA�C��̃T���S��j�����Ă��邱�Ƃɒ��~�̎w�����o���A����ɏ]��Ȃ���Ζ��ߗ��ĂɕK�v�Ȋ�ʔj�Ӌ����������ӌ��ł�����B��N�Ĉȍ~�̖��ߗ��ĂɌ������H���̋��s�ɑ��āA���m���I�E�O�c�@�I�ł̈������Ӗ�ÐV��n���̖��ӊm��ɂ�������炸�A�H�����ĊJ����Y�p�̊���j�����邱�ƂɁA���Ɍ��m�����u�������������v���f�������̂��B
����ɑ����{�����̉�����ӔC�҂̐����[�����́A�u���{�͖@�����ƁA���̊��ɋy��Łc�A�l�l�Ɛi�߂�v���J��Ԃ����B����ł́u����Ɋ��Y���A��n���S�y���ɓw�߂�v�ƌ����Ȃ���A�m���I�ȍ~���{�t���͒m���Ƃ̖ʉ�����ۂ��Ă���B���̏�Ɂu���ē����̂��߉���͓��{�S�̂̋]���ɂȂ�v�ƌ����B�@�����ƂƂ����O�ɖ����`�̍��ł���Ȃ��A�ƍٍ��Ƃł͂Ȃ��̂��B
��N�V���ȍ~�̍H�������ł͂Ȃ��B�V�Q�N�Ԋ҈ȍ~�ǂꂾ���E�]���������Ă����̂��B�P�X�S�T�N�̉����ł̋]���B�����̗��������ƍc���������B�P�U�O�X�N�̎F���N�U�ȗ��S�O�O�N�B�u���̊��ɋy��ł܂����{�i���}�g�j�̋]���ɂȂ�v�Ƃ����̂��A����ȁu�@�����Ɓv�͊肢�������A�Ƃ����̂������ʂɏZ�ނP�S�O���l���̋��ʂ̎v���ł͂Ȃ��̂��B
�Q�P���ɂR�X�O�O�l�̍R�c�W��
����ɐ旧���Q�P���A����s�����̕l�łR�X�O�O�l���W�܂�H�����~�����߂��W��J���ꂽ�B��N�V���ɐ��{�����ߗ��čH���Ɍ����ĊC��{�[�����O�������n�߂Ă���A�S��ڂ̑�K�͏W��B���̏�Ō����\���ĎQ���������c�c���m�����A����h�q�ǂɍ�Ƃ̒��f�����߂Ă�����������Ȃ����Ƃɑ��u�{����o����B�����`���Ƃ̂�邱�Ƃ��v�Ɣᔻ�����B�܂��W��ɂ͌��I�o�̍���c���������䖼��s�����Q�����A����o�g�̓����̑�w�����A�u��n�͂���Ȃ��A�����������Ƃ͂��������ƌ������v�Ɣ��������B�T���ɂ͖��]�̏W����J�Â��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B
���{�����̋��������ƑS�ʑΌ���
�R���Q�R���̉����m���̌��f�ŕӖ�ÐV��n��͐V���Ȓi�K�ɓ������B����h�q�ǂ͂Q�S���A�u�m���̎w���v����������߁A�_�ѐ��Y�ȂɐR���𐿋������B����͖@����܂߉��ꌧ�ƈ��{�����̑S�ʌ��˂ƂȂ�B���܂������i��s�����čH�����~�߂Ȃ��ƁA���i�v�I�ȑ�K�͊�n�̌��݂��i�ށB�S�E�Q�W����f�[����A�T�E�P�T���a�s�i�A�U�E�Q�R�ԗ�̓��Ɍ����A����A�т̍s�������|�I�ɋ������悤�B
���ۂ̂��߂ɕČR��n���K�v�ƌ����Ȃ���A�����̑I����ɗU�v����Ǝ咣���Ȃ������Ƃ�]�_�Ƃ̖��ӔC�Ȍ����������Ă͂Ȃ�Ȃ��B��������ƍقɐi�ސ����ɂ́u�S���Ɏ����m�炴��A���Ȃ킿����S���v���A�l���͎����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�������A�H�����s�A�����ĉғ��A���@�����Ƃ������{���������ƑΌ�����A�l���̑����N�����߂��Ă���B
�Ӗ�Ì��n�ƈ�̂ōs��
�u�ł��鎖�����ł���낤�v
���
 |
�R���Q�P���i���j���ꌻ�n�ł̓����Ɍĉ����āu�Ӗ�ÐV��n���݂��Ƃ߂悤�I ��㓯���A�N�V�����v�����s���ŊJ�Â���A�Q�O�O�l���Q�������B�Ăт����́u�r�s�n�o�I �Ӗ�ÐV��n���݁I ���A�N�V�����i�P�T�c�̂ō\���j�v�B
�L�����v�E�V�����u�Q�[�g�O�ʼn̂��Ă���uWe shall overcome�v���R�锎������̐��i�^���j�ŗ���钆�ŁA�W��͊J�n���ꂽ�B
�`���A���ꌻ�n���痈�㒆�̊C�����L�������B����h�q�ǂ�C��ۈ����ɂ��\�͓I�e�����܂��܂��������Ȃ�C��U�h�A�܂��Q�[�g�O�ł͌��x�@�����A���Ԍx�����A�ĕ��̒e�����͂˂̂��ē����������Ă���ƕ����B
�����Ă��̊ԁA�Ӗ�Ì��n�ɂ��������R�l�̕�����ƌ��ӂ�����A�����Ƒ����̐l���삯���V��n���ݍH�����Ƃ߂悤�ƌĂт������B�i���J���p�̗v���������Ȃ��A�Q���ґS���ŁuWe shall overcome�v���̂��W���グ���B
���ꂩ�璆�p
���ɁA��ォ�牫�ꌻ�n�����ɎQ�����Ă�������烊�A���^�C���Ō��n�̗l�q���������p�ŕ��ꂽ�B����s�����̕l�ɂR�X�O�O�l�����W�A�������m���̑㗝�ŕ��m���̔���������A���O�����͂��߂ďW��ɎQ���������Ƃ����ꂽ�B�Ō�ɁA�W��̂܂Ƃ߂𒆖k�����Y�������Ȃ��A�A�����J�̎��ّO��ʂ�f���s�i�ɏo�������B�i�ʐ^�j
���̓��̏W��́A���ꌻ�n�ł̓����Ɍĉ����č�N�W������T��ڂ̏W��B�W����e��f���A�V���v���q�R�[���ɂ��Ă��n�ӍH�v���A�������U�h���J��L���錻�n�U�h���x���A���ɓ������߂ɌĂт�����ꂽ�B�Ӗ�ÐV��n���ݍH�����~�߁A�ČR��n�P���܂œ����������ӂ��ӂ��W��Ƃ��Ă��������ʂ��ꂽ�B
���̊ԁA���ł͋ߋE�����h�q�ǂւ̏�����o�A�Ӗ�Ö��ߗ��čH���������听���݂ւ̍R�c�E�\������s���A��T�Nj�C��ۈ��{���i�_�ˎs�j�ւ̍R�c�s���������Ȃ��Ă���B�����\��n�ł̊C��j�~�s����Q�[�g�O�ő̂��ē��������Ă��錻�n�ɉ����A���ł��ł��鎖�����ł���蔲�����B
���͂�ƍٍ���
���@�E����֘A���s��
�R�E�Q�P�`�Q�R����
 |
| ���@�O�̕Ӗ�Ê�n���݂������Ȃ��s�� �i�R���Q�R���j |
���ꌧ����s�����̕l�łR���Q�P���ɂR�X�O�O�l���W�߂Ă����Ȃ�ꂽ���ꌧ���W��Ɍĉ����āA�Q����̂Q�R���A�����ŁA�u�Ӗ�Ê�n���݂������Ȃ��I �R�E�Q�R���@�O�s���v�����g�܂ꂽ�B�Ăт������̂́A�q�Ӗ�Âւ̊�n���݂������Ȃ����s�ψ���r�A�q����E��ؔ���n���֓��u���b�N�r�B
�@���҂ɂ��R�c�s�����I�����Ԃ��J��グ�Ă���ɍ����B�W�܂����l�͂R�O�O�l���z�����B�u����̔����{�s���ɂ͂P���U��l���W�܂����B�s���̈��{�ւ̓{��͒��_�ɒB���Ă���v�u���͂�ƍٍ��Ɓv�u�푈���ł��鍑�ł͂Ȃ��A�A�����̂悤�ɐ푈�����Ȃ��琶���鍑�A�푈�Ȃ��ł͑��݂ł��Ȃ����ɂ��悤�Ƃ��Ă���v���̐������������B���n�Q�[�g�O����̒��p�ŁA�R�锎������́u�����m���̍H����~�v���ɂ���̓I�ڕW�������ē������Ƃ��ł���B�x�@�E�C��ۈ����͂ǂ��Ή�����̂��B����̓����͂������܂�悤���Ȃ��v�ƌ�����B
�����ł������̒c�̂��l�X�Ȏ��g�݂������Ȃ��Ă���B�S���̗͂ŕӖ�ÐV��n���݂�j�~���悤�B
 |
| �R���Q�Q���A�u���{�����m�n�I�O�R�Q�Q��s���v�ɂ͓���J�`������ӂłP���U�O�O�O�l���Q������ |
 |
| �R���Q�P���A�u�W�c�I���q���@�����j�~�A���{��|���I�����s�����I�v�f���������Ȃ�ꂽ |
�Q��
���{�����̑Θb���ۂɓ{��
12���@�C��{�[�����O�����ĊJ
�Q���Q�U���A�Ӗ�ÐV��n���݂̓{�[�����O�����Ɍ����ăN���[���D�⎑�ނ�ς�D���t���[�g���ŏ����ɂ������Ă���B���̓����ꌧ�́A�h�q�ǂɂ���ėՎ��������ɐݒu���ꂽ�R���N���[�g�u���b�N�ɂ���ʔj��ɂ��Ă̒����ɓ������B�W�J�������A�P�J���ŃR���N���[�g�u���b�N�ɂ��T���S�̔j����m�F�����B���͂���Ȃ钲���̂��߂ɗՎ����������̒��������߁A�h�q�ǂɗ�������̈�����v���������A�ČR�͗��������F�߂Ȃ������B
�e���g�̍U�h
�܂��A�Q�U�������̃L�����v�E�V�����u�Q�[�g�O�̃e���g�P���ɂ��āA�s���̓Q�[�g�O�̃e���g���A���̂܂܍���������Ō��������Ɉړ����āA�V���ɋ��łȃe���g��ݒu�����B�k�������������́A���̏ꏊ���_�����ƌ����A�P����v�����Ă����B�����āA�����Ȃ̎w���̂��ƂQ�S���Ԃ̊Ď��̐����n�߂��B����ɂ������āA���ꑍ�������NJJ�����ݘJ���g���́A���ꑍ�������ǒ��ƊJ�����ݕ����ɂQ�S���ԊĎ��̐��̉��������߂�\������������Ȃ����B
 |
| �C��Ń{�[�����O���������s���Ă���X�p�b�g��D�i�R���P�R���@����s��Y�p�j |
�C�ۂ̖\��
�R���P���A�X�p�b�g��D�Đݒu�ɂނ�����Ƃ��i��ł���B�C��ł͍R�c�D�ƃJ�k�[�����R�c�B�Q�[�g�O�ł͂P�O�O�l�ȏオ�R�c�B�C���Ƃ����n�����R�Q�[�g�ł́u�{�[�����O��������߂�v�ƍR�c�̐��������A�C��s�����Ɂu�Ӗ�Ãu���[�撣��v�ƃG�[���𑗂����B
�S���A�J�k�[���̏������~�}���������B�����͊C�ۂɍS�������ہA��ʂ̊C�������Ԃ�A���̂܂܂P���Ԕ����u���ꂽ�B�����Œ�̉��ǂɂ�����̒������������̂��B�ق��̃����o�[���C�ۂ���S�����ɖ\�͂��ӂ���Ă���B�܂��A�R�c�̏��^�S���{�[�g�ɊC�ۂ̑�^�S���{�[�g���̓����肵�A�s���ɃP�K�킹�Ă���B
�P�Q���A�{�[�����O�����ĊJ�B��N�X���P�T���ɐł̃{�[�����O�������I�����Ĉȗ��A�U�J���Ԃ�̒����ĊJ�ƂȂ����B���̒��f�v�������A�s���̍R�c�����S���������B���`�̊��[�����́u�������������̂ŏl�X�ƊJ�n�����v�Əq�ׂ��B���{�����̂Ȃ�ӂ�\��ʂ����ɁA�s���̓{��͔��������B
�C��ł͍R�c�D�ƃJ�k�[���t���[�g�ɋ߂Â��������R�c�B�C�ۂ͍R�c�D�ɋ����ɏ�荞��A�J�k�[���m�ۂ��A�J�k�[�����S�����Ă���B���̍U�h�ŏ������P�K�������B
�Q�[�g�O�ł�
�Q�[�g�O�ł́A�{�[�����O�����ĊJ�O���猃�����R�c�s���������Ȃ�ꂽ�B�Q�[�g�O�ɍ��荞��ōR�c�A�@�����ɂ��ڂ������ɂ��������x�����荞��ōR�c�B���˂��邱�Ɛ��\���A����ɑ���𐮂��邽�ߏW����J�n�����ӂ��ł߂�B�W��̂P�O�������뒲���ĊJ���m�炳���Ǝs���̓Q�[�g�O�ɓ˓������荞�B�@�����͑��������s���ɏP��������B���ڂ��������n�܂�A���������Ō��˂���B�R�O���ɂ킽�范�������݂����B���̌�A�}�������s���������Q�O�O�l���R�c�̏W����J�n�B�����āA�C���Ƃ����n�����R�Q�[�g�Ɉړ����A����Ȃ�R�c�̐����������B
�Θb�����ۂ��鐭�{
�����m���́A���{�̋��d�p���Ɂu��ψ⊶���B�������i����g���ĕӖ�ÂɊ�n�点�Ȃ��Ƃ�������̎����Ɍ����Ď��g�ށv�ƌ��ӂ�\�������B��䖼��s���́u���̒m���������̒��~��\������Ă���̂ɁA�������������Ȃ��B��̉��Ȃ̂��v�Ɠ{���\�����B
�P�R���A���J�h�q���́A�m���Ƃ̑Θb�ɂ��āu����Ă��Ӗ��͂Ȃ��v�ƁA�Θb�����ۂ����B�{�[�����O�����͑�D�������ĂR�J���Ɋg��B�C��ł͍R�c�D�R�ǁA�J�k�[�P�S�����R�c�s���B�Q�[�g�O�ł͘A���̌������R�c�s����W�J�B
���ꌧ���ƑS���̗͂ŐV��n���݂�j�~���悤�B
���l���c��ɍR�c�s��
�ĉғ����ӂ�e�N
�R�E�Q�O
�R���Q�O���A���l���c��͉�����̂��̓��ɑS�����c����J���A���l�R�E�S���@�̍ĉғ��ɒ��c����ӂ��邱�Ƃ����߂悤�Ƃ��Ă����B���l�E��ь����ĉғ��j�~�l�b�g�́A�O���P�X�����獂�l�Ńr�����T�����l�����ƁA���̖�ɋ삯�����l�����Ƃ��u�ዷ�̉Ɓv�ō������A�Q�O�������́A�ԂR��v�P�O�l�ŌߑO�W���߂��ɍ��l������ɋ삯�����B
�X������̒��c��S�����c��ɂ������A���Δh�c���𑗂�o���������ŁA�j�~�l�b�g�Ɣ��Δh�̍��l�����͖�����ӂōR�c�E��`�����𑱂����B���c��͌ߑO���̖T���Ȃ��̑S�����c��ŁA�c�����������c��c���P�R�l�̂����A���͂P�l�ŁA�P�Q�P�ōĉғ��ɍ��ӂ��A�������Ă�Œ��c��̈ӌ���`�����B
�T���Ȃ��甭��
�ߌ�̒��c��ɂ́A�j�~�l�b�g�̂P�O�l���T���ɓ������B���c��̖`���ɋc�����A���c��ǂ������o�܂ōĉғ��ɍ��ӂ����̂����P�O�����炢�����Đ��������B
�������I������i�K�ŁA�T���Ȃ���j�~�l�b�g�̐V�J���A�u�c���A�T���Ȃ���ł͂���܂����A�Q�_�ӌ����q�ׂ����Ă��炢�܂��v�Ƃ��Ƃ���������Řb���n�߂��B�E�������~�ɓ��������A�u�P�_�ڂ͒��c��͍ĉғ��ɍ��ӂ����ȏ�A����N���邱�ƂɐӔC�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������ƁA�Q�_�ڂ͒��c��͌����̂Ȃ�����W�]���Ă����ӔC�����邱�Ɓv�𔗗͂������Đ��������̂ŁA���c����E���������̍Ō�܂ŕ����Ă����B
�V�J����̔����I����A�j�~�l�b�g�͑ސȂ����B
�u�����~�̈��͂ɕ������P�O�O�O�l
�R�E�Q�P�s�\�z���l����s����W��
 |
| ���V������ɏW�܂����P�O�O�O�l�̎s�� |
�R���Q�P���u�ǂ����悤�H ���s���Ȃ��Ȃ�����\�s�\�z�E�Z�����[���l����s����W��\�v�����s������̂��l����s���̉��ÂŊJ�Â��ꂽ�B���V������ߐs�����ĂP�O�O�O�l�߂����Q�������B
�W��̓s�A�m�̒e����肩��n�܂�A��Òc�̐��b���̒����i���J��̂������������Ȃ����B�u�������́A�}�h�A�M���A���ʁA�E�Ɠ����āA���̂ƂĂ��d�v�ȏZ�����[�ɂ��āA�㐢�ɒp���������Ȃ����[���Ɠ��[���ʂ��o�����Ƃ��ƂĂ�����Ǝv���Ă��܂��v�u�^�����ΈȑO�ɓ��ʋ�ݒu���菑�̓��e��m���āA�����b�g�A�f�����b�g���[���ɗ������āA�V�O���ȏ�̓��[����B���������B�^���̐l�����̐l�������̂Ȃ��Z�����[�ɂ������v�ƏW��̎�|���q�ׂ��B
�u�����~�̂�������
�����ė\�肳��Ă������䑏���s��w��w�@�����̍u�������O�Œ��~�ɂȂ������Ƃɂ��āA���s�\�z�̓��e�ȑO�Ɍ��_����������Ă���̂ł͂Ȃ����A���䋳������̐������ɏd�v�Ȃ��Ƃ�������Ă���ƑO�u�����āA���̕�����ǂݏグ���B�܂��A���䂳����r�f�I�ŎQ���҂Ɂu���l�тƐ����v�������Ȃ����B����ɂ��ƁA���s�\�z�ɂ��Ắg�V�̎����h�\���Ĉȗ��A�Ζ����Ă����w��ݍ�e���r�ǂɓ���̌��I�������͂��爳�͂�������A�܂��A����Ŏ��₳���悤�Ȏ��Ԃɂ܂łȂ��Ă���B����ŁA����ȏ㔭���̋@��D���Ȃ��悤�u�����Ƃ��߂�Ƃ������Ƃ������B�����̈��͂����������̂��낤�Ɛ�������B
�������A���̂��Ƃ��t�ɍl����ƁA���䋳���̎w�E�͐������̂ŋ����ƈېV�̉�ɂƂ��ĕs�s���Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ��B���䋳���̎咣�̓l�b�g�œ�����������ǂނ��Ƃ��ł���B�ނ������g�V�̎����h�̂����̂P���Љ��B����́A�����̔ɉh�́u�s�v�Ƃ��������݂̂����ł͂Ȃ��A�u��ɏW���v�̎����ł��A�Ƃ������́B
�s�\�z�Ɛl�̕�炵
�����ăt���[�W���[�i���X�g�ő�㒩�������u�L���X�g�v�̃R�����e�[�^�[�ł�����g�x�L�����o�d�B�{���͓��䂳��ƑΒk�̗\�肾������ł����ƑO�u�����āA�u�s�\�z�̂R�̃L���ƌ��ʂƂ��Ă̐l�̕�炵�v�Ƒ肷��u�����s�����B�L���Ƃ����̂͒��Ɠǂ݂����Ă��ǂ��B�����̂ŗv�_�̂݁B
�@�s�s�̌`��ς��邱�Ƃƌo�ς̔��W�͂܂������̕ʂ̘_���B�o�u�����A���͂����b���������̂Ƃ����s�͂Ȃ������B
�A��d�s�������Ƃ������������������邱�Ƃ��d�s���Ƃ͂���Ȃ��B
�B�ېV�̉�́u�j�A�C�Y�x�^�[�v�Ƃ����āA�Z���ɂ₳������b�����̂Ƃ�������ǁA����͘_�������������B�����s����l�ő��s���S���̖ʓ|������Ȃ��A�T�l�̎������猩���Ƃ������A����͌��t�̃}�W�b�N�B���ڎs���ɂ��̂������l�͂��Ȃ��B���ۂɍs���ɑ��Ă��̂������Ƃ��͖����̑������A�������Z�ޒ��̋c���B���ꂪ�u�j�A�C�Y�x�^�[�v�B���s�����{�ɑg�ݍ��܂�Ă����s���Ƀ����b�g�͂Ȃ��B
���̂��ƏΕ����|�т�����ŏ��̂����ɋ����ᔻ���`�N���A�W��錾�����ĕ���B
�V�N�ȏW��
�I����Ă�����l�������̂ŁA�X�^�b�t�̈ē��ɏ]���ďo���ɋ߂��Ƃ��납�珇���ޏ�B�Ȃɂ��W��Ȃꂵ�Ă��鎄�����̏W��Ƃ͏�������āA�i�s�Ƃ����r�[�ɒu���ꂽ�ł������J���p���Ƃ��V�N�������B���ꂩ����������������I�ɓ����l�����ɂ���āA�����Ȋ�悪�s��������Ȃ��Ǝv���B�i���R�j
�W��錾�F�T���P�V���́A�������̑��s�����ł��邩�ǂ��������߂�ƂĂ���ȏZ�����[�ł��B�{���ɓ�����ł͂���܂����A���l�Ȉӌ����A��l�ЂƂ肪�A��������Ǝ����̓��ōl���A�������q�X���X�̂��Ƃ��\���ɍl�����āA���[�ɍs���܂��傤�B����̐l�ɐ����|�������āA����قǏd�v�Ȗ��Ɋ������邱�ƂȂ��A�V�O���ȏ�̓��[���ŁA�ӎv�\�������܂��傤�I
�R��
�J���҂̎��Ԃ��ی��Ȃ��D��
�V���ȘJ�����Ԗ@�������ȁi��j
�X��@���n
�u�g�c�Ƒ�[���h�ƌ����Ă��܂����A���̖{���͂����ł͂���܂���B������ł������ԓ������āA�J���҂̎��Ԃ��ی��Ȃ��D�����Ƃ��ł��A�����������K�v���Ȃ��A�J���҂̎��Ԃ��x�z�ł��邱�Ƃɂ���܂��v�u�V���x�́A���{�œ����J���҂̖��ƌ��N���������댯�Ȃ��̂ł���A�ߘJ������������g�ߘJ�����i�@�h�ł��v�B����͐V���ȘJ�����Ԗ@���ɂ��鞥��Y�ٌ�m�i���{�J���ٌ�c��C�����j�̎w�E�ł���B�{�e�ł́A�R���Q���A�J�������R�c��i� ������Y�c�勳���j�����\�����J��@���̉������߂����@�Ă̗v�j������������j�I�ȍU���̈Ӗ��𖾂炩�ɂ��A���{�����Ȃǂ̂��܂������e��ᔻ����B
�J�������R�c��́u����̘J�����Ԗ@���݂̍���ɂ��āv�Ƒ肵���������܂Ƃ߁A�Q���P�R���Ɍ����J����b�Ɍ��c�����B���e�́u���荂�x���Ɩ��E���ʌ^�J�����i���x�v���t�F�b�V���i�����x�j�v�Ȃ�V�������x�̑n�݂ł���B������ē��R�c��̘J���������ȉ�ƈ��S�q�����ȉ�ŐR�c�������Ȃ��āA�P�V���̎��₩��P�J���̃X�s�[�h�i�Q�U���A�Q�V���A����E���\���܂߂Ă��S���Ԃ̐R�c�j�œ��\���ꂽ���̂ł���B
�u���x�v���t�F�b�V���i�����x�v�Ƃ́A���̗v���������J���҂ɂ��āA�J��@�̘J�����ԁE�x�e�E�x���E�[�銄�������Ɋւ���K�����܂������K�p���Ȃ����ƂƂ�����̂ł���B��P�����{�����i�Q�O�O�V�N�j�ŘJ���҂́u�c�Ƒ�[�����v�Ƃ̓{��̒��ŁA�v�j�����ꂸ����ꂽ�u�z���C�g�J���[�G�O�[���v�V�����v�i�z���C�g�J���[�J�����ԋK���K�p�Ə����x�j�̏o���Ȃ����ł���B��������̏t�ɂ��t�c���肵�A������ɒ�o�����������A�Q�O�P�U�N�S���Ɏ{�s���悤�Ƃ����̂ł���B
�J���ҕی�̍�������
����͍��E���Q�O�O�T�N�́u�o�c�A�v�ȗ��A�O��ɂ��Ă������̂ł���B���{���t�́u���{�ċ��헪�v�i�Q�O�P�R�N�U���t�c����j�̒��Ɂu���������v�v���ʒu�Â��A�@�h���@�����A�A�J�����Ԗ@�������A�B���ق̋��K���������N�̉ۑ�ɂ��Ă���B���̑�P�e�Ƃ��ĂW���ԘJ��������̂��鐧�x�̓������d�����Ă����̂��B����̘J��@�����ɂ͍ٗʘJ���E�t���b�N�X�^�C���Ζ��̊��ԋK�����O�����e���܂܂�Ă���A�J���҂��u���ʁv�ŋ��킹�A�W���Ԃ��ē������Ƃ�J�����s�ɂ��悤�Ƃ����_�������m�ł���B�O���[�o�����{�̌���Ȃ��J���ҍ��̗~�]�ɂ������悤�Ƃ����̂ł���B
���{�͂Q���P�Q���̎{�����j�Łu���ȗ��̑���v�v�̂ЂƂƂ��āu�_����l�ȓ������v�u�J�����Ԃɉ��I�Șg���͂߂�]���̘J�����x����юЉ�̔��z��傫�����v�v���邽�߂ɁA�u�V���ȘJ�����Ԑ��x��I���ł���悤�ɂ���v�Əq�ׂĂ���B�u��Ƃɍv������l�����܂��B���������l�ɂƂ��ẮA�J�����ԋK���͕s�v�ł��v�i����L�Ɛ_�ˑ�w��w�@�����Q�E�P�S�u�����V���v�j�\���ꂪ�_���Ȃ̂��B
���E�Ɠ��{�̘J���҂��������������ƌ��Ɗ��ŏ������A�Œ��Ƃ����u�W���ԘJ�����v�̑匴����ł����Ƃ����̂ł���B�܂��ɗ��j�I�U���ł���B�J���ґ������j�I�������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�J���^���̌���͌��������A���́u�J�����Ԗ@�������v�ɂ͓��ꂵ������������g�����Ƃ����@�^�����܂�Ă��Ă���B�u�t�c����E�����o�������ȁv�̂���������������O�ŋN�������B
�O�Ҍ����̔j��
�܂��A���\���ɂ͘J���ґ�\�i�V�l�̑��Ӂj�̔��Έӌ��i�u�F�߂��Ȃ��v�j���Y����ꂽ�B�����������Ƃ͏]���͂��肦�Ȃ��ٗ᎖�Ԃł���B�{���J������̐���͐��{�ψ��i���v�ψ��j�A�J���҈ψ��A�g�p�҈ψ��ŋ��c���Č��߂�Ƃ����̂��h�k�n�Ȃǂō��ۓI�Ɋm�����Ă��郋�[���B������A�J�������R�c��ł��O�ҍ\���ŐR�c�Ɠ��\�������Ȃ��Ă����B�J���ґ�\�̔��Έӌ��݂ɂ���A�u�O�Ҍ����v�����Ƃ����̂����{�̓ƍَ�@�ł���B�h���@�����̍ۂɂ����̂������Ƃ�ꂽ�B����A�J��@�̍��{��ς���d��Ȗ@�ĂŁA���̓ƍَ�@�����s�����B
�����ԘJ���̍��@��
�v�j�ɂ́u�ΏۋƖ��ɏA�������Ƃ��́A�J��@�S�͂ɒ�߂�J�����ԁA�x�e�A�x���A�y�ѐ[��̊��������̋K��́A�K�p���Ȃ����̂Ƃ���v�Ə�����Ă���B�u�K�p���O�v�A���ꂪ����I�ɂȂ�̂ł���B�u���Ԃł͂Ȃ����ʂŕ]���v�Ɛ��{�͐������邪�A�_���́u�W���ԘJ�����v�́u���O�v���ړI�Ȃ̂ł���B�u�c�Ƒ�[���@�āv�Ƃ����ᔻ�����邪�A���Ԃ͂��[���ł���B�u�c�Ɓv�A�u�x�e�v�A�u�x���J���v�Ƃ����T�O���̂��̂��Ȃ��Ȃ�Ƃ������ƂȂ̂ł���B�K�p���O�ɂ́A���ł��o�c�҂ɗ��ꂪ�߂��Ǘ��E�ɓK�p�����u�Ǘ��ēҁv�����邪�A�[��J���̋K���͂�����B�V���x�͂�����Ȃ��Ȃ�̂ŁA�[��J���ɂ����~�߂�������Ȃ��Ȃ�B
���܂��܂ȁu���N�[�u�v���Ƃ�Ƃ����Ă��邪�A��������f�^�����Łi��q�j�A�x�e���x�����Ȃ��A�����ԓ������Ă��������Ȃ��Ƃ������������{����ɂ������Ƃ������Ƃł���B�ŏ��́u�ΏۘJ���ҁv�̌�����Ă��邪�A�u�W���ԘJ���v�̌�������̂���A�J�����Ԑ��x�̍������ύX�����̂ł���B���ꂪ�����ǂ̂悤�Ȍ��ʂ������炷�̂��B�W�O�N��Ɏd�|����ꂽ�{���֎~�̔h���K������J���̓������₪�đS�J���҂����A������E�ߘJ���E�n���ɒǂ���������Ƃ��݂�Ζ��炩���B
���s�̘J��@�́A�g�p�҂͘J���҂ɁA�x�e���Ԃ������P���W���ԁA�T�S�O���Ԃ��ĘJ�������Ă͂Ȃ炸�i�J��@�R�Q���j�A���A�����Ƃ��Ė��T���Ȃ��Ƃ��P���̋x����^���Ȃ���Ȃ�Ȃ��i�J��@�R�T���j�ƒ�߂Ă���B�g�p�҂��J���҂ɑ��Ă������J���i���ԊO�J���E�x���J���j�𖽂��邽�߂ɂ́A���Y���Ə�̘J���҂̉ߔ�����g�D����J���g�����Ƃ̋���i������R�U����j���������K�v������ƂƂ��ɁA���ۂɎ��ԊO�J���E�x���J�����������Ԃɉ����āA�����������x����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�܂��A�J�����Ԃɉ����Ĉ��ȏ�̒����̋x�e���Ԃ�^���邱�Ɓi�J��@�R�S���j�̂ق��A�g�p�҂��J���҂ɂ������Đ[��i�ߌ�P�O������ߑO�T���܂Łj�ɘJ���������ꍇ�ɂ����ẮA�ʓr�A�[�銄���������x�������Ƃ��`���t�����Ă���i�J��@�R�V���j�B
���̍Œ����߂��J��@��E�@���Ă����Ƃ��������ł��邪�A���������E�@�s�ׂ����@�����悤�Ƃ����̂��B���̐��x���n�݂����A�����ԁE�ߏd�J���ɂ����������������K���͎����A�ߘJ���₤�a�Ȃǐ��_�����̌����������ȂǁA�����̘J���҂̐����E���N����@�ɂ��炷���ʂƂȂ邱�Ƃ͊m���ł���B
�ΏۘJ���ҋK��͞B��
�J���R�̕����悭�ǂ߂A�����Œ�Ă���Ă���̂��u���ʌ^�v�J�����ł͂Ȃ����Ƃ��킩��B�x����Ă����Ȃ��B���ł́A�u���x�v���t�F�b�V���i�����x�v��n�݂��闝�R�Ƃ��āA�u���Ԃł͂Ȃ����ʂŕ]������铭��������]����J���҂̃j�[�Y�ɉ����v�Ƃ����Ă���B�}�X�R�~�ł��u���ʂŒ��������܂铭�����v��u���ʌ^�J�����v�Ƃ������\�����g���Ă���B�܂��A�ΏۘJ���҂̑z��ɂ��āu���Z���i�J����f�B�[�����O�Ɩ��v�u�R���T���^���g�v�u�����J���Ɩ��v�Ȃǂ��������A�u�ꕔ�̘J���҂Ɍ��肵�����́v�Ƃ�����ۂ��L�����Ă���B�����������x������Ƃ��Ɏg����퓅��i���B���łɊe��̐��ʎ�`�����̌n��ٗʘJ�����A�t���b�N�X�^�C�����̉��œ����J���҂͂T�O���߂��ɋy��ł��邱�Ƃ�����A�˂炢�́u���ʌ^�v�J�����ł͂Ȃ����Ƃ͖��炩���B
���{�́u���~�߁v�O��
�v�j�ɂ́u���x�̐��I�m����K�v�Ƃ��A���̐�����]�����Ă������ʂƂ̊֘A�����ʏ퍂���Ȃ��ƔF�߂�����̂Ƃ��āA�����J���ȗ߂Œ�߂�Ɩ��v�Ƃ�������������Ă��Ȃ��B����͂ǂ̂悤�ɂł����߂ł���B�Ⴆ�A�C��R���e�i�A���̃h���C�o�[�̋Z�\���u���x���m���v�Ƃ������Ƃ��ł���B�܂�N�ł��ΏۂƂ����B������������߂�̂́u�@���v�ł͂Ȃ��u�ȗ߁v�ł���B�����J����b�̌����Ŕ����邱�Ƃ��ł���ȗ߂ŁA���ۂɓK�Ȑ������\�Ȃ̂��傢�ɋ^�₪����B�܂��A�����ɁA�g�p�҂��ΏۘJ���҂ɑ��āA�ΏۋƖ��͈̔͊O�̋Ɩ��𖽂����ꍇ�ɁA�J���҂����̋Ɩ����߂����ۂł���̂����肩�ł͂Ȃ��B���{�̖\���Ɏ��~�߂�������Ȃ��B
�ȏォ�疾�炩�Ȃ悤�ɁA�u���ʂŒ��������܂铭�����v��u���ʌ^�J�����v�Ȃ�\���͌��ł���B�V���x�̂��ƂőΏۘJ���҂́u���ʁv���ǂ̂悤�Ȋ�E�葱�ɂ���ĕ]������A���̌��ʂ������Ƃǂ̂悤�Ƀ����N�����̂��Ƃ������_�ɂ��āA����v�j�ł͑S��������Ă��Ȃ��B������Ă���̂́A�J�����ԋK�����u�K�p���Ȃ��v�Ƃ������Ƃ����ł���B�V���x�̉��ł́u�������v�Ƃ́A�����ɒ����ԓ����Ă��A��������������ۏ�͂Ȃ��Ƃ������̂ł���B�v����ɁA�u�c�Ƒ��Ȃ��Ă����J���ҁv�̑n�݂ɉ߂��Ȃ��B�܂�����{���قȂǂŁu�i��]����J���҂́j�j�[�Y�v�Ƃ����Ă�����̂��A�{���ɂ���̂��Ƃ�����肪����B���̂悤�ȐV���x�̑n�݂𐳓������闧�@�����͂Ȃ��B�����ĐV���x�ɑ���J���҂̃j�[�Y�����݂��Ȃ����Ƃ͖��炩���B�i�Â��j
�S��
�n���҂̓��ӂȂ��܂�
�����p�����̒����E�����J�n�i��j
���ˁ@�k��
�R���P�R������A��������F���ɐ݂���ꂽ�ۊǏ�ւ̏����p�����̔������J�n���ꂽ�B�����A�o�t���̕ۊǏ�ɂ������ɔ������J�n����\�肾�������A�o�t��������R�c�̐���������A�J�n���������ꂽ�B����ǂ��W�J���邩�͗\�f�������Ȃ��B�u�ۊǏ�v�͂����܂ł��ꎞ�I�Ȓu����B�����p�����������E��������u���Ԓ����{�݁v�̗p�n�擾�́A�܂��S���i��ł��Ȃ��B�n���҂Q�R�O�O�]�l�̓��ӂ��Ȃ����炾�B�������m�����F�E�o�t�����̎̎���\�����傫������Ă��邪�A�̐S�̒n���҂œ��ӂɑ����������̂͌����_�܂��Q�R�O�O�]�l���������P�l�B�n���҂̑唼�����ɂ��������Ă��Ȃ����B�ɂ�������炸�A���́A�����p�����̔������J�n�����B
 |
| �Z��������̏�ŁA���ȂȂǂ̊��������Ɍ������āA�ӌ����q�ׂ�u���Y����k�ʐ^�����̋N�����Ă���j���l�B��N�U���P�� |
�����������ŁA�n���҂̂P�l�ŁA���̒n�ʼn����������Ɣ_�Ƃ̎u���Y����i�����j�ɂ��b�����B
�u���̂����ɔ[���������Ȃ��v
���ꂪ�u�ꂳ����͂��߂Ƃ���n���҂̗����ȋC�������B
��N�̐�����Œn���҂���o���ꂽ�v�]��ӌ��ɑ��āA���͓����Ă��Ȃ��B����ǂ��납�A������ȍ~�A������̎u�ꂳ��ւ̘b�́A�d�b���P���������B���ӂ������Ȃ��B�����āA���́u�R�O�N�ȓ��Ɏ����o���v�ƌ����Ă��邪�A�����������`�ł��܂������Ƃ�������ɁA�u�ꂳ��͕s�M������Ă���B�p�n�擾���i�܂Ȃ����Ƃ�n���҂̂����ł��邩�̂悤�ɐ��_���d�����A��Ўғ��m�f����悤�Ȃ����ɂ������Ă���B
�ӂ邳�Ƃ��������ꂽ��ɁA����ɂ��̂ӂ邳�Ƃ��i�v�ɒD����ꂵ�݁B����ɑ��č��͌����������Ƃ��Ă��Ȃ��B���̂��Ƃ��u�ꂳ���n���҂͑i���Ă���B
�u�ꂳ��́A�܂��A�u�����S�̂ŕ��S���������āv�Ƒi���Ă���B���Ԓ����{�ݖ��́A���ƒn���҂Ƃ̊Ԃ����̖��ł͂Ȃ��͂����B�Ƃ��낪�A�����̑命���ɂƂ��đ��l���ɂȂ��Ă��܂��Ă���B�����̑命�������������ӎ��ł��邱�Ƃɂ���āA�傫�Ȕ�Q�����҂ɁA������x�A��Q��^����悤�ȗ��s�s���܂���ʂ낤�Ƃ��Ă���B�����ĉ����̌����ҁE���Q�҂炪�A�����������ƂR�ƌJ��Ԃ����Ƃ��Ă���B
�����p�������ǂ��Ɏ����Ă����̂��Ƃ�����̓I�ȋc�_�ɓ���O�ɁA�������ɂ́A�l����ׂ����Ƃ�����B
�u�ꂳ���A�o�t���A��F���̒n���҂݂̂Ȃ���̐��Ɏ����X���Ăق����B
�܂����̘b���������Ȃ��̂�
�\�P�R������A�ꎞ�ۊǏꏊ�ւ̔������n�܂�܂��B�k�C���^�r���[�͂R���V���l
�u��F�Ȃ�������悤�ɁA�ǁ[���ƍs�����Ƃ��Ă���ˁB��������������āA��Ђ��Ă��鎄����A�}���������Ƃ��Ă���킯�ł���B
�n���҂͂Q��R�S�l���炢���ȁB���̒n���҂̓��ӂ���炸�ɁA�ǂ���A���̂����B���炭�O�ɂ͂ˁA�u�n���҈�l�ЂƂ�ɂ������Ɏf���܂��v�Ƃ����Ă����̂ɁB
�\���N�̂T�`�U���A���ɂ��Z��������A�܂��X�`�P�O���ɒn���Ґ���������Ȃ��܂������A���̌�A�ǂ̂悤�ɐi�߂��Ă����̂ł��傤���H
�u��F�n���Ґ�����̂Ƃ��͂ˁA������́A�u���������̐�����ǂ����邽�߂ɁA��F����Ƒo�t����ɂ����b�ɂȂ�Ȃ�����Ȃ�Ȃ��B���������������v�Ƃ������Ƃ������ˁB�����ăv�����g��n����ĂˁA���c���P���āi�u�j�Ȃ�ځA�����Ȃ�ځA�R�т��Ȃ�ځB��������A������A�������̊������ƒႢ�B���̑O�̂T�����āA����ɂƂ��Ă͔��l�ȉ�������ˁB
�u�V���ɓy�n�������āA�Ƃ������āA�������ĉ�������v�ƌ����Ă��ˁA���̊�ł́A�y�n�͔����Ă��A�Ƃ͌����Ȃ��̂�B���킫�s�����Č��������āA�����ƍ����킯�B�Ȃ��ړ]��̉��i����ɂ��Ȃ����āB�ŁA�y�n�������ljƂ������Ȃ�����؋�����ƂȂ邯�ǁA�݂�ȍ�����Ă��邩��A��s������݂��Ă���Ȃ��킯�ł���B
����Ȃ˂��A���˔\���Ȃ�����̌̋��ɏZ��ł����̂ɁA�Ȃ�����ȒႢ�l�i�ނ��āB�n���Ґ�����̂Ƃ��A�u���̐����ł͉Ƃ͌����Ȃ���B���������ĉ������v���Č��������ǁA���́u�A���āA���������Ă��������܂��v�Ƃ��ꂾ���B
�\�����������ʂ́H
�u��F�����ς���Ă��Ȃ��ˁB
�\�n���҂̕��Ɍʂ̐����́H
�u��F�Ȃ��ˁB�A�����d�b������B���Ȃ���ˁB�u�n���҂̕���K�₵�Ă��܂����A�����ȂƂ���ɔ��Ă��āA�킩��Ȃ��l�����Ď��Ԃ��������Ă��܂��v�ƁB�킩��l���ɂ�������ˁB
�u�ŁA���̂Ƃ���͂�����ɂȂ�܂����H�v���Đu������A�u�u�ꂳ��̂Ƃ���͑啪�x����ł����c�v�ƁB�u�����A�����ł���B�ł��A�ł���Α����ˁv�B
�����������Ƃ肪�������B���ꂪ�����Ԃ�O�̘b������B����ȍ~�A���̘A�����Ȃ��B
�Z����������P�Q��ɕ����Ă���āA�����͖{�C�ɂȂ��Ĉӌ�����������ˁB�ł��A���ꂪ����͂��ĂȂ��B����͏�Ȃ��ˁB
�\���ǁA������ȍ~�A�����牽�̘b���Ȃ��̂ɁA�P�R������������n�܂�ƁB����͑�ςȂ��Ƃł��ˁB
�u��F�R���R���̐V���i��������u���Ԓ����{�݁v���W�j�ɂ́A�T�^�{�݂Ƃ��A�U�^�{�݂��Ƃ��A���Ԓ����{�݂̔z�u�}���o�Ă��ˁB�������܂������Ƃ̂悤�ɂˁB�܂��b�����������Ďn�܂��Ă��Ȃ��̂ɂ���B����n���҂͖�������Ă��B
���ꂩ��A�u�ꎞ�A��̂���Q��͍Ō�ł���v���Ă��Ƃ��V���ɏ����Ă���B���x�̂R���P�P�����Ō�ŁA�����p�����̔������n�܂�����A������Q����ł��Ȃ��ˁB���₢����ꂿ�Ⴄ�ˁB����ȏ�Ԃ������瑛����B
����ˁA���肪��������ˁB���ꂪ���Ԃ̈�Έ�̘b��������A����Ȃ��Ƃ͐�ɐ��藧���Ȃ��ł���B�i�Â��j
�������ٔ��̖T����
�S���P�V���A�P�P�� ���n��
�S���P�V���ߑO�P�P��������n�ق̑�@��ŕی����������ጛ�i�ׂ̑�P������٘_���n�܂�B���I�ɂȂ邱�Ƃ��\�z�����̂ŖT����]�҂͂P�O���R�O���ɑ��ٌ�m��قP�K�ɏW�܂낤�B
�����������������T�P�l
���N�A�ی����������ɂ������đS���łP���l����R�������������Ȃ��A���ł͑S���ő��̂P�V�W�S���̐R�������������Ȃ�ꂽ�B�ȗ��A�S���ői�������i�߂��P�V�̒n��ői�ׂ���i����Ă���B
����A���ł͂T�P�l�������Ƃ��ė������������B�N��͂R�Q����W�O�A�j���Q�W�l�A�����Q�R�l�ł���B����ŃK���a����p�s�\�ƂȂ����l���A���̂��܂�̂����ɕ���A�����ɉ�������B�����͌����������ی�o�b�V���O�̂Ȃ��A�������������l�����ł���B
�J�������Ɛ����ی�
�����ی�Ɠ��{�̗ȘJ�������Ƃ͖��ڂɊW���Ă���B�ȉ��A��N�̐R���������̌����ӌ��q�̂Ȃ����炢�����Љ�����B
���J�Ђ������
�ʊ|���s�\���ŗ������S���������ĉE���b�Ǝw�Ӎ��܂����N���[���I�y���[�^�[�̂`����́A�J�Ђ��K�p���ꂽ���J�Е⏞�ł���ƂȂ���فA����ɗ���ǂ��o���ꂽ�B�u���������炤���Ƃɂ͈����ڂ�����A�D���D��ł�����Ă���l�Ԃ͂��Ȃ��B������̂ł���Γ����������ǁA�a�C�łł��Ȃ��̂Ő����ی�Őg�̂������Ă������ƕ邵�Ă���l����������Ƃ������Ƃ��킩���Ăق����v�Ƒi����B�g��������A���k�ł���Ƃ��낪����A���ق◾��ǂ��o����邱�Ƃ��Ȃ��������낤�B
���V���O���}�U�[
�u��Q�ҁv�̎q�ǂ��������A�{�c�Z��ɉ��債�Ă����ꂸ�A���h��������N�r�ɂȂ�A�{��̂��ꂪ�Ȃ��a����B
�����������Q�`�R�J���œ���������A�������A�ߘJ�Ŕ]�[�ǂɂȂ����B����ȏ�ߖ�ł���Ƃ���͂Ȃ��B�n�����҂ɂ͐l�炵�������錠���͂Ȃ��̂��ƕ���b����B
�����������̂ŗǂ������̎d����T���������d�����x��ł܂Ŗʐڂɍs�����A�������q�ǂ�������ď����̕s���������Ȃ��c����B
���܂��߂ɓ����Ă���N��
�S�O���N�����Ȓ��H��ł܂��߂ɓ����Ă��N���͌��z�Q�U�O�O�O�~�B����ȏ㉺����ꂽ�琶���Ă����Ȃ��Ɠ{��d����B
�����������Ă������Ȃ�
�S���a�Ől�H�قƂȂ苁�E���������Ă��邪�d�����Ȃ��B�������A�����̂��Ƃ����łȂ��S�̂̂��Ƃ��l���āA�Œ�����̈����グ����Ƒi����e����B
���l�Ԃ̑�����ے�
�P���Q�H�A�����������炵�A���C�����炵�Ă���B�ǂ�Ȑߖ�����Ă���̂��������Ă���̂��ƕ���f����B
�u��Q�ҁv�̐����錠��
�����ی�́u��Q�ҁv���l�炵�������Ă������߂̓y��ɂȂ��Ă���B�]���}�q�P���̂g����͉�҂���ł���悤�ɕ��C��g�C���͕ʎd�l�̍L���Ƃ��낪�s���B�������A�{�c�E�s�c�Z��ɂ͏����ɂ����Ƃ��낪�Ȃ��B���߂�ꂽ�ی��̉ƒ����ɏ�悹���Č��ԕ��̓���Â��Z�܂������낤���Ċm�ۂ��Ă���B
�������A�ی��艺����ꂽ�炻����Ȃ��Ȃ�B�{�݂���Љ�ւƂ������̕��j�Ȃ̂ɁA�ی���艺����ꂽ�������x�{�݂ɖ߂邵���Ȃ��ƕ���g����B
�Ǘ����邱��
�n���̋��낵���͂������Ȃ��Ȃ邱�ƈȏ�ɌǗ����邱�Ƃł���B�V���̍w�ǂ���߁A�ߏ��t����������߂Ă����ΐl�͌Ǘ�����B�ی��艺���͂����������Ԃ��ڂ���ɐ��݂����B�N�z���h�����i�Q�O�O�W�N��j�̑̌��ł��l�͌Ǘ��������]���玀��I�Ԃ悤�ɂȂ�B����ȎЉ�ɂ��Ă͂����Ȃ��B
�Љ��ς���ٔ�
���A���{�͎��q���̊C�O�h���A�����U���ȂǗ��j�I�ȕ���_�ɗ��Ă���B���������Ȃ��A�l���l�炵���������Ȃ��A�n�����҂��܂��܂��n�����Ȃ�悤�ȎЉ�͕ς��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
����E�C�������ė������������T�P�l�̌����ٌ͕�c��x���҂Ƌ��ɁA���̎Љ��ς��悤�Ƃ��Ă���B�����̕��X�̖T�������肢�������B�i��c�j
�T��
�����̊g��Ǝi�@���
������������}���u����
�R�E�P�R�� ��
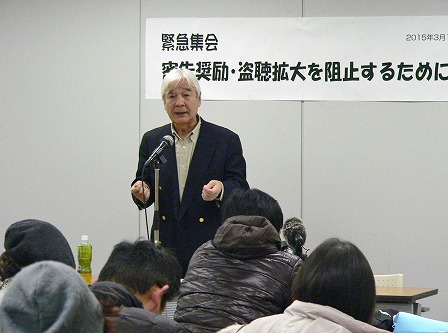 |
�R���P�R���A���s���Łu��������E�����g���j�~���邽�߂Ɂv�Ƒ肷��u���W��A�q���d�߂ɔ�����s���A����E���r�̎�ÂŊJ���ꂽ�B�u���͊֓��w�@��w���_�����̑������������i�ʐ^�j�B�㔼�͑�������Ɖi�����v�ٌ�m�Ƃ̂��Ƃ�Ŗ��_��[�߂��B
�܂���������́A�����@�����Ă��܂ށu�Y�i�@���ꕔ�����āv���t�c���肳�ꂽ���̓��ɋً}�W������Ȃ��Ă���Ӌ`���m�F���āA�ŋ߂̏��Ƃ��ĂR�_�������B
��͂f�o�r�i�ړ��ǐՑ��u�j�{������n�ق��u�K�@�v�ł���Ƃ������ƁB�f�o�r�{���K�@���g�傷��Ǝԗ��ǐՑ{��������I�ƂȂ�{�����@���܂������ς��B
��͊����Z���Ύs�����E�������ߔ����B�s������т��Ė������咣���A���߂ƂȂ������A���d���͍߂�F�߁A�L�ߔ����B���̗L�ߔ����̗��ɂ́A���d���̕ʂ̃E�\���B������i�@����̉\��������B
�O�͌Y�i�@���ꕔ�����ėv�j�̔����i�R���V���j�ł���B
���̏�œ����̊g��Ƃf�o�r�Ǝi�@����i�����Ԃ�߂��y������j�����ŁA����܂ł̑{�����@��傫����E���鎟���ɌY���i�@�����邱�ƂɌx���𗐑ł����B�܂�����܂ł̍U�h�ł͋Ȃ���Ȃ�ɂ�����}�������Ă������A���݂̍���ł͑S���_��ɂȂ��ĂȂ����Ƃ��A���٘A�̖�萫���܂߂Ēe�N�����B
�{���@�ւ̏Ă�����
���؎����i���@�̏؋���₁j��u�z�u�����i�x�@�̋����j�Ƃ������͔ƍ߂������āA�@���R�E�V����̌Y���i�@���ʕ���́A����X�Q���Łu�ߔN�̌Y���i�@���߂��鏔����Ɋӂ݁A����ɑ������V���ȌY���i�@���x���\�z���邽�߁A��蒲�y�ы��q�����ɉߓx�Ɉˑ������{���E�����݂̍���̌�������A��^�҂̎�蒲��^���E�^��̕��@�ɂ��L�^���鐧�x�̓����ȂǁA�Y���̎��̖@�y�ю葱�@�̐����݂̍���ɂ��āA���ӌ������肽���B�v�Ƃ����B
���̎���ő{���̉������i�ݑ{�����@���ς��Ǝv������A������e���Ӑ}�I�Ɏ��Ⴆ���x�@�E���@�́A�u�����{���ł̙l�߂�h�����߁v�ɁA������ǐՁi�f�o�r�ݒu�j��i�@������\�Ƃ���V�{�����@�����A�{���@�ւ̏Ă�����ւƐi��ł����B
�����č���̌Y�i�@���ꕔ�����ėv�j�ł́A���s�����@���{���Ă��炢�����̕���Łu��ށv�����Ȃ���A���̗��Ŗ\�͒c�̑g�D�I�ƍ߂ɌW���Ƃ��镪��i�ޓ��A�����A�����v�����A�d�q�v�Z�@�g�p���\�A�����j�ł͓������g�傷��A�V���ȌY���i�@�v�j�Ă��o���Ă����B�����F�߂�A�K�p��\�͒c����Љ�^���S�̂Ɋg�債�Ă����̂͌��͎҂̏�ł���B�u�g�D���v����ɂ��Ă���_�ł́A���݂̒e���ł��Ƃ��ȒP�ɍٔ������u���d�v��F�肵�Ă���_�Łi����e���ł͌���ɂ��������ŋ��d�������j�A�x�@�E���@�E�i�@���������������Ă��邱�Ƃ�����B����A��������܂�Ă���u�i�@����v�́A���Ԃ�����߂��y������A���邢�͖Ƒi�Ƃ������̂ŁA�č��̎i�@����Ƃ͓����ł͂Ȃ��B�l�߂̉����ł���A���ƌ��͂ɂ��ł�����������������B
�e���̊g���
�㔼�́A�����@�̍���A�f�o�r�ݒu���F�J�����̖�萫�Ȃǂɂ��Ę_�c���ꂽ�B���ɂf�o�r�ݒu�Ƃ�������O�����Ƃ̖��Ȃǂ����A���Ɍ���A�����̑{����@�͌��@�R�T���̗ߏ��`�Ɉᔽ����ƒe�N���ꂽ�B�܂������Ȃǂ͏�ɂ܂��u���Љ�I���́v�ɓK�p����邪�A���ɂ͎Љ�̕ϊv�����߂�^�����u���Љ�I���́v�Ƃ���e�����g�債�Ă����B�܂��i�@����ٌ͕�m�����ӂ��A���鑤�ٌ̕�m�Ɣ����鑤�ٌ̕�m�֔��W���Ă������̂ŁA���٘A�̓_���Ȃ��̂̓_���A�ƌ�����K�v������B���d�߂͍��͓����Ă��Ȃ����A�Q�O�O�U�N���d�ߕ��ӓ����̓���������I�ŁA���̓������p���ׂ����Ȃǂ̓��_���i�B�Ō�Ƀe�����Y�����@��A�}�C�i���o�[�@�̖�萫�Ȃǂ�����E�A�s�[���̂Ȃ��Ŋm�F���ꂽ�B
���肾������̓��e���������A��������̔���₷���b�̒��ŁA�����̒e���̍U�h�_���悭�킩��W������B
���ʁE�r�O��`�ɂm�n
���̂���A�т̂��ߓ��_�W��
�ɉE���{�����ɂ���āA�W�c�I���q���̖@�����Ȃǂ̐푈�������ɐi�߂��Ă��邪�A���̂悤�Ȑ����̂Ȃ��ɔ����C�V�Y���E���w�C�g���ʒu�Â��Ă�����������낤�Ƃ�����|�łR���V���A�����s���œ��_�W��J���ꂽ�B��Â͍��ʁE�r�O��`�ɔ�����A����B
�����C�V�Y������Ȋ����ۑ�Ɍf���Ă���킯�ł͂Ȃ�����ǁA�������傫�Ȋ֘A�������L���Ă���^���̈�̐l�X���p�l���X�g�Ƃ��Ĕ��������B�쌴�h�ꂳ��i�w�C�g�X�s�[�`�ƃ��C�V�Y�������z���鍑�ۃl�b�g���[�N�j�A�V�F�ꂳ��i���V�c���^���A����j�A���s�ꐬ����i���{�@��w�u�t�j�A���c�T�삳��i�u���A�E�l�������̎������I�v���s�ψ���j�A�x������i��������������n�x���j�Ǝ�Î҂̃����o�[�B
�����_�ւ̊댯
��O�I�ȉ��l�ςŐ������E�Ɏ����Ă������Ƃ�����{�����ɂ������āA���̕��a�ȉ��l�ς��ے�������̂Ƃ��āu���x�����Ȗ��m�V�c�v�������o�����ƂőR���悤�Ƃ���X����A���邢�͍��h�n��J�g�̊����������l���A���̓l�b�g�E���ɂȂ��Ă���Ƃ������Ⴉ��́A�Љ�̂��E�ɑ傫���X���Ă��邱�Ƃ��悭�킩��B
���̂悤�ȂȂ��ł́A�傫������オ�锽���C�V�Y���E���w�C�g�̂������������̊낤�������Ă���Ǝw�E���ꂽ�B���Ƃ��A���C�V�X�g�ɑ���u���{�̒p�v�Ƃ����R�c�̌��t�́A�w�C�g�ւ̓{�肪�����I�����_�ɗ��ߎ����댯������B�܂��A�u���ǂ����悤���v�̃v���J�[�h�́A�������ʂ��l����ۂ̓��{�l����̉��Q�Ґ���B���ɂ���Ƃ������ƂȂǂ��B
�����̘_�_�́A���C�V�Y����w�C�g�Ƃ̂����������A����ԈႦ��ΓV�c���⍑�ƂƂ��������̘g�g�݂ɋz�����ꂩ�˂Ȃ��낤��������Ƃ������Ƃ��w�E���Ă���B���̂��Ƃւ̎��o�Ǝ��g�݂����߂���B
���̂̂���A�т�
����A�ʂ̎�������̌������w�E����Ă���B�u�i�w�C�g�́j���{�l�Ƃ��Ēp���������v�Ƃ������t�͍ݓ��R���A���ɂƂ��Ă͂��ꂵ�����t�ł��邵�A�u���ǂ����悤���v�̃v���J�[�h���A�����������̌���ł͓����҂Ɍ����Ă͈Ӗ��̂��錾�t���B�܂��A�u���Z����������̒��N�w�Z�r�����l���鎞�A��͂莩���͓��{�l�Ƃ��Ēp���������Ǝv���v�Ƃ����������������B
�����́A����Ό���ł̒����I�Ȋ���낤�B���ƁE�V�c���E���Q�����Ƃ����̂́A���������ۉ��Ȃ��ɂ��̘g�g�݂̒��ɒu����Ă��܂��Ă��闧�ꐫ���B���̂��Ƃ�������ƂƂ炦�Ԃ��āA��������傫�ȕ����������Ȃ�������Ȃ��Ǝv���B
�����ŁA���C�V�Y���ƒ��ʂ��Ă��錻��ŁA�l���s���ւƓ������A�����������`��銴�����B
���̗��҂��ǂ̂悤�ɐ��������炢�����A����Ȃ��Ƃ�����������W������B�i�s�j
�함����͖���
��㍂�� ���W�L�ߔ���
�֓d�O����e��
�R���X���A�u�֓d�O�e���i�P�P�E�P�U����ߕ߁j���c����v�̍T�i�R����������A��㍂�ّ�Q�Y�����i���c�M�V�ٔ����j�́A�P�R�L�ߔ�����j�����A�V���ɗL�߂̕s�������i�ꕔ���i�j�����������B
�P�R�����́A�u�������s�W�Q�A�함����v��F�肵�A�����P�O�J���A�����Z���P�U�O���A���s�P�\�R�N�ł��������A���̓��̔����́u�������s�W�Q�v�݂̂�F��A�����U�J���A�����Z���P�U�O���A���s�P�\�Q�N�������B
�P�J���ȏソ���Ă���ߕ�
�Q�O�P�Q�N�P�O���T���A�֓d�{�X�O�Łu�����̍ĉғ�����߂�v�ƍR�c�����������Ȃ��Ă����ۂɁA�������Ă��Ȃ��`���u�]�ь��W�v���ł����������ߕ߂���A���S���ԂŘA�s���ꂽ�B���̍ۂɁA����ɂ��������̎Q���҂��A���̑ߕ߂ɓ{��A�A�s�ԗ��ɂ������R�c�����B�R�c��U����āA�x�@�ԗ��͂`�����A�ꋎ�����B
���ꂩ��S�O���ȏ���������P�P���P�U���̒��A���c����͓ˑR�A����ŗߏ�ߕ߂��ꂽ�B�e�^�́A��L�R�c�s�����u�������s�W�Q�A�함����v�Ƃ������́B�함����Ƃ́A���c���x�@�ԗ��ɍR�c���Ă����ۂɁA�A���_�[�~���[�ɂӂꂽ�u�ԃ~���[���͂��ꂽ�̂ŁA���̏�Ōx�@���Ƀ~���[��n�����Ƃ����������A���c���A���_�[�~���[�����Ƃ˂��������̂ł���B
�u�함����v�ł���������
���ٔ����́A�������s�W�Q�ɂ��Ď�����P�R�����P���A�L�߂Ƃ������̂́A�함����ɂ��Ắu�ƍ߂̏ؖ����Ȃ��v�Əq�ׂ��B
���c���x�@�ԗ��̃A���_�[�~���[������������Ƃ��錟�@���咣�ɑ��āA�����́A�u�{���A���_�[�~���[���̂́A�{���Ŏ��O���ꂽ��A�����ۊǂ���Ă��炸�i���F�x�@�������̏�Ŏ̂ĂĂ��܂����j�A�{���ł́A�����F�肷��肪����������Ă���A�ނ���{���ԗ��͕����i�}�}�j�Q�Q�N�Q���ɍw������A�����̕p�x�Ŏg�p����Ă����ƔF�߂��A�{���܂ł̎g�p��������ɂ���ẮA�v���X�`�b�N���̎����A�Ђъ�������͎���Ɍ`��̕ω����������āA���x�����Ȃ��Ă����\����ے肷�鍪�����Ȃ��؋��ƂȂ��Ă���B�v�u�퍐�l�̖{���A���_�[�~���[�ɑ���s�ׁi���F���@���咣����A�����������Ƃ����s�ׁj�͂����F�߂邱�Ƃ��ł����A���s�ׂ�F�肵�Ċ함����߂̐�����F�߁A�܂��A���̍s�ׂƔ퍐�l��̖{���ԗ��ɑ���s�ׂƂ���A�̂��̂Ƃ��ĕ���Č������s�W�Q�߂̐�����F�߂���Ԕ����ɂ͂��̔F��ߒ��Ɍo�������ɏƂ炵�ĕs�����ȂƂ��낪����A�����ɉe�����y�ڂ����Ƃ����炩�Ȏ����̌�F������B�v�Ƃ��A�P�R������j�����A���炽�߂āA�������s�W�Q�݂̂�F�肵�A�L�߂Ƃ����B
�j�S�_�����ꂽ�u�������s�W�Q�v
���ٔ����́A�`���A�s����邱�Ƃɏ��c���R�c���u�x�@�ԗ��̑O������ʼn����A���̏���ȑ����K���X����Œ@�����v�Ƃ����s�ׂ��������s�W�Q�ɂ�����ƔF�肵���B
����Ȃ��Ƃőߕ߂���A�V�J������������A�������ɗL�ߔ����Ƃ͂Ƃ�ł��Ȃ����Ƃ��B
���������A���̌��́A�A���_�[�~���[���͂���Ă��Ȃ���Αߕ߂ɂ܂Ŏ����Ă����Ȃ��������ĂȂ̂��B�A���_�[�~���[���͂��ꂽ�Ƃ����������g���āA�u�함����A���W�v���˂��������̂ł���B������A���̃A���_�[�~���[���������߂ɂȂ����Ƃ������Ƃ́A�����������̒e�����R�̍��������ꂽ���Ƃ��Ӗ�����B
�Ƃ��낪�A�����܂ŗL�߂��ێ����邽�߂Ɂu�x�@�ԗ��̑O������ʼn����A���̏���ȑ����K���X����Œ@�����v�Ƃ����s�ׂ�ƍ߂ł���Ƃ����̂��B
����Ȕ����́A�F�߂��Ȃ��B����Ȓe�����܂���Ƃ���Ȃ�A�s���^���̂��܂��܂ȏ�ŁA�s���������x�@���Ɲ��݂������Ƃ͕p�ɂɋN�����Ă���A�����̍s�ׂ͂��ׂđߕ߁��������ٔ����L�߂ɂȂ肩�˂Ȃ��Ƃ��������͂�ށB
�㍐���Ă�������
���c����͂��̕s���������͂˂������ׂ��㍐�����B�㍐�R�Ŋ��S���߂�������낤�B
�U��
����
�~�߂悤�u�e���v�푈�@�����ȑC�X�����r�O��`
�w����v�z�x�R���Վ������� �����W
�w�V�������E�G�u�h�P���^�C�X�������l�������̏Ռ��x��ǂ��
���� ���E�i�Ƃ肢 ���������j
�{���́A���X�����l���ɂ������āA�����鍑��`�����̘J���Ґl�����Ƃ�ׂ���������ނ����ŁA�w�����x�̓ǎ҂ɓǂ�łق����{�ł���B
�P�E�P�P���C�X�����̊����f��
�P���V���ɁA�w�T���V�������x���P���������N�������B�A���W�F���A�o�g�̈ږ��Q�����A�ҏW�҂�x���ȂǂP�Q�l���E�Q�����B�����P���̎����͂P���X���ɋN�������B�}���o�g�̈ږ��Q�����H�i�X���P���A���_���l�S�l���E�Q�����B
����ɂ������A�t�����X�S�y�łR�V�O���l�Ƃ�������f�����g�D���ꂽ�B���Љ�}�⋤�Y�}�A�̓}�ȂǍ����E���h�T�c�̂��Ăт����A���@���X�����A�ێ��}�̃T���R�W���哝�̂������A�u������v�v�̏W��E�f���ƂȂ�B
�Q���҂́A���̎�̖\�͂ގЉ�͂��₾�Ƃ����ӎ�����Q�����Ă���B�������A�����{�͂�����u���a���s�i�v�Ɩ��Â��A�u�t�����X�ɂ�������U���v�u�\���̎��R�ɂ�������U���v��O�ʂɏo���A���C�X�����r�O��`�̐��肽�ĂƁA�u�e���푈�v�ւ̋�����v��}�����B�����{�́A��N�V���̃C�X���G���ɂ��K�U�����ւ̍R�c�f�����A�U�P�N�A���W�F���A�Ɨ��x���̃f���ȗ��A���߂ċ֎~�����B�u�\���̎��R�v�ɂ�������_�u���E�X�^���_�[�h�����܂����B
�������f���ɂ́A�K�U�̋s�E�ҁE�C�X���G���̃l�^�j���t�ƁA�p���X�`�i�̃A�b�o�X�c���A����Ƀt�����X���R����������}���̘��S�哝�̂��ĂB�I�����h���哝�̂́A���̃f���ƈ�̂ŁA���u�V�������E�h�S�[���v����ŁA���̋����u�e���v�푈�̂��߂Ƀy���V���p�ɔh������Ɛ錾�����B
�X�̎Q���҂̎v�������ƋV�������A�w�Z�ȂǂŖقƂ����������A�P���P�P���������̋L�O���ɂ����B�V���������ɂ�������]���͑傫�����Ă����ɂ�������炸�A���{�́A�V�������x�����Ӗ�����gJe suis Charlie�h�u���̓V�������v�Ƃ����X���[�K�����A�������Ȃǂɋ��������B
�V���������́A�V�O�N��ɍ����E�A�i�[�L�X�g�n���Ƃ��đn�����ꂽ���A�Q�O�O�P�N�ɕҏW���������Ă���A�����ς�C�X����������M����ᑭ�ȓ��e�ɓ�������B��e�҂ɂ��C�X���G���x���̃l�I�R���I�l�����������B�Q�O�O�U�N�̃C�X���G���̃��o�m���N�U���x�����A�p���X�`�i�̑�Q���C���e�B�t�@�[�_����B���̂悤�ȃV�����������A�����{�͎�����A���Ǝ����ʼn������A�R�������x�̔̔��������ꋓ�ɂV�O�O�����ɂ��Ȃ��Ă���B
�����ƒm���l�̕���Ƌ�Y
�����{��`�V�}�Ȃǁu�ɍ��h�v�S�c�̂́A�u�\���̎��R�Ɏ^�����A�_�������ɔ�����v�Ƃ���R�~���j�P�\�����B������v�ŁA�C�X�����ւ̓G���S�������邱�ƁA�t�����X�̃C���N��}���A�����A�t���J�ւ̌R������ւ̐������ɍR�c���Ă���B�������u�\���̎��R�Ɏ^���v�Ƃ��ăV��������e�F�����B����́A���ƓI�r�O��`�ɋ������Ă���ƌ����Ă��d�����Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�{���̖`���Ɍf�ڂ��ꂽ�T�l�̘_�l�������悤�ɁA���āA�Ƃ��Ƀt�����X�̒m���l�́A���̎����̕]�����߂����Đ^����Ɋ���Ă���B
�o���o�[���́A���X�����ւ̍U���A�r�˂ƁA���{�̌R������ɔ����Ă���B���̂����Łu�W�n�[�f�B�X�g�v��ᔻ���A��������̂̓��X�����̉ۑ�ł����āA�X�����̔C���̓C�X�����ւ̓G�ӂ�U���Ɠ������Ƃł���Ƃ���B
�o�f�B�E�́A���X������G������V��������ᑭ�Ȑl�퍷�ʂƔᔻ���A���Ƃ��V�������x���̃f���Ăт����A���߂������Ƃ�f�߂��Ă���B
�`�����X�L�[�́A�鍑��`�E�V�I�j�X�g�����N���ҁE�s�E�҂ƒf�߂���B�P�X�X�X�N�A�m�`�s�n�R���~���V�F�r�b�`�����x���̌��_�����E���邽�߁A�Z���r�A���c�����ǂ����A�P�U�l�̃W���[�i���X�g���E�Q�������Ƃ�Ꭶ���Ă���B
�l�O���́A�r�O��`�E���̐��͑���Ɏ��~�߂���������Ƃ����y�Ϙ_�ɗ����ĂP�E�P�P�f�����m�肵�A�u��Q�ҁv�ł���V�������ɘA�ѕ\�����Ă���B
�W�W�F�N�́A�P�E�P�P�f�����u�U�P�I���U�v�ƌĂԁB�������P���ҁE�u�e�����X�g�v�E�u������`�ҁv���ČR���{�݂��U�����Ȃ����Ƃ�ᔻ���A�ނ������炩�炭��u�C�X�����\�t�@�V�Y���v�Ɣᔻ����B
�O�R�҂͕����{�E�鍑��`�E���X�������ʂɔ��A�V�������ɂ͔ᔻ�I�A��Q�҂ɂ͕����{�E�鍑��`�E�C�X�����r�O��`�ւ̔ᔻ���Ȃ��B�l�O���̓V���������u���ԁi���u�j�v�ƌĂсA�W�W�F�N�́u�e�����X�g�ᔻ�v�ɏI�n����B
�u���_�̎��R���A�e�����v�H
�{���ɂ��A�t�����X�ł͂��̂悤�ȂQ���Η����l����l�͂قƂ�ǂ��Ȃ��B���_�̎��R�͖@����{�ɂ���Ď���Ă��炤�Ƃ͍l���Ȃ��A���������ē��������̂Ƃ��čl���Ă���B�V�������̕ҏW�҂��炻���ł���B���ɁA�����̘_�҂��A�u�\���̎��R�v�u�r�u�M�̎��R�v�܂��́u�@���̑����v�̑Η��̖��ƍl���Ă���B�C�X�������E�ɕ��f���������މ\��������_�Ō��E�����邪�A�u���_�̎��R���A�e�����v���]���ł��闧��ł��낤�B
�w�i�Ƃ��āA�t�����X�ł́A�l��▯���ɂ������鍷�ʕ\���͖@���ŋK������邪�A�@���ւ̕��J�ɂ͋K�����Ȃ��B�����_����`�I�����͏�������邪�A�C�X��������l�|���錾���́u���_�̎��R�v�ƌ��Ȃ����B���X�����̏����������̏ꏊ�ŃX�J�[�t�����Ԃ邱�Ƃ͋֎~�E�ߕ߂���邪�A�L���X�g���k���\���˂̃l�b�N���X�𒅂��Ă���������Ȃ��i�������ڗ����Ȃ��Ƃ������R�Łj�B
�����ł̓V�������ւɂ��Ă���A���u�̐����w���҂�@���w���҂��u���a���f���v�ɎQ�������B�ނ�́A�u�E�l�Ȃǂ̔ƍߍs�ׂ̓C�X�����ł͂Ȃ��v�Ƃ����B����������̓A���u�⃀�X������O�̈ӎ��Ƃ͂�������Ă���B���̓_�́A�{�������̎���[�q�̘_�l�ɏڂ����B
�l���������āA���{�ł́A���{��ᔻ����ƁA�u�C�X���������A�܂��̓e�����x������̂��v�Ƃ��Č��_�E��������肾���ꂽ�B�ǔ��ƎY�o�́A�А��ł�����咣���������B
�{���Ɉ��p����Ă���L���N�̘_�l�ł́A�u�e�����Y���v�́A�u�����I�w�i���������\�͂�ƍ߂̃R�[�h�ɓ]�ʂ��邽�߂́v�l�|��ł���ƌ����Ă���B������āA���c�l�́A���͂�̐��ɔ����閯�O�A�Ƃ��Ƀ��X�����̖\�͂��u�e���v�ƌĂсA����ɂ�������푈���u�e���Ƃ̐킢�v�Ƃ��Đ��������邱�Ƃ�ᔻ���Ă���B�Ƃ��Ɂu�e�����X�g�Ƃ͈�،����Ȃ��A�v���ɉ����Ȃ��v�Ƃ��āA���̎咣�̐�����c�_���邱�Ǝ��̂��ւ��邱�Ƃ�ᔻ���Ă���B
���{�́u�e���v�푈�ւ̎Q��̗���ɞ������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�t�����X�Љ�ƃ��X����
�P���V���ɃV���������P�������N���V�Z��A�P���X���Ƀ��_���l���X���P�������N���o���[�́A�Ƃ��Ƀt�����X�̋��A���n�o�g�̈ږ��Q���ł���B
�����̔w�i�ɂ̓t�����X�ɂ�����u�x�O�v��肪����B�t�����X�����ɂ̓��X�������U�O�O���l����i�l���̖�P���j�A�Ƃ��Ƀp���̂Q�O�Έȉ��̎�҂̂S�T�������X�����ƌ�����B�ނ�͑�s�s���ӂ̍x�O�ɏZ�݁A���ʂƊi���E�n���ɋꂵ��ł���B�Ƃ��Ɉږ��Q�A�R���́A�A�E�E���Z�E�����E�w�̍��ʂ������A �A�C�f���e�B�e�B�̔��D�ɋꂵ��ł���B������ɁA�ɉE�E�t�����X��������Ȃǂ����̂悤�Ȉږ������ʁA�r�˂��铮�������߂Ă���B
��N�T���̉��B�c��I���ł́A���Y�}�n�̘J�g�b�f�s�̑g�����̂S�l�ɂP�l�����E�y���̍�������ɓ��[�����Ƃ����B���C�X�����̔r�O��`�A�ږ��r�˂̐����́A���{�ł͑z����₷��B�������Ώۂ�����Ă��邾���ŁA���{�ł��ݓ������{���̐l�̔r�O��`�͓��l�̂Ђǂ��ł͂Ȃ����B
������
�{���ɂ��A�C�X���������C�T�̃��X�����̏P�������ɂ��āA�u�P���C�X�����ƈ����C�X�����v����ʂ���Ƃ��āA�C�X�����f���A�ᔻ������X��������B�����`��l���Ƃ��������l�ς����ɁA�ȂŐ�̂��B����́A�u���e���v�푈�̗���ɞ��������̂ł͂Ȃ����B���ՓI�Ȑl�ԉ���̗���A���Y��`�̗���́A��}��������}�����A�s�E���Ă��鎩���̒鍑��`�Ɠ����ׂ��ł���B������Ƀ��X�����l���̐M�����������Ȃ��B�����łȂ���A��Q�A��R�́u�l�������v�̔����͕s�����B�R���P�W���̃`���j�W�A�����͂��̒����ƍl������B
�ǎ҂̐�
�G�R��X�g�[�u�� ���т𐆂���
�w�����x�i�P�U�X���A�Q���T���j�ɁA���ܘb��́w���R���{��`�x�̏��]���ڂ�܂����B���̒��ŏЉ��Ă���a�c�F�����L���������s�A�V�P���̍u����ƃG�R�E�X�g�[�u�Â���ɎQ�����܂����B�{�ɂ��ʐ^���ڂ��Ă��܂��B�Q�O���b�g���̃y�[���ʂ��㉺�Ɍq���A���ɉ��˂�ʂ����ɓy����Ǎނ��l�߂������̊ȒP�ȍ\���ł��B
�ł��オ�����X�g�[�u�ɂ��������S�������悹�A���т𐆂��Ă݂܂����B�g�������Ƃ̊��蔢��͂�A�͂�}��R���ɁA�킸���Q�O����Ő����オ��܂����B�R����̓[���~�ł��B���̐������Ă̂��т��A�d�C���Ő������̂Ƃ͐H���������Ԃ�Ⴂ���������̂ł��B���݂��d������`�������Ȃ������A�������̔т�H�ׂ�Ƃ����B���������邱�Ƃ��ł��܂����B
�q�R�E�P�P�r����܂�S�N�B��n�k�A��Ôg�̔�Q���r��Ȃ���A�����N�����ꂽ���d������ꌴ���̑厖�̂́A����Ƃ��Đi�߂��Ă��������̊댯�𔒓��̂��ƂɎN���܂����B�A�����J�͐�㐢�E�̐����哱���邽�߂Ɋj����Z�p�̓]�p�Ƃ��āu���a���p�v�̖��̉��Ɍ����𐄐i�B���{����̐���̉����ł�����ۑ̐����ŁA���������Ƃ����T�W����̌��������݂��܂����B
�S�̃v���[�g�������A���f�w�������ɑ���ΎR�ł�������{�ɁA�l�Ԃ̋Z�p�Ő���ł��Ȃ��j���d�𗐑����u���x�o�ϐ����v�������Ȃ��������{�̎Љ�̂��̂�����܂����B���܈��{�����́A�W�c�I���q���̍s�g�e�F�A�C�O�h���ɂނ����Ӗ�ÐV��n���݂����s���悤�Ƃ��Ă���A�܂�Ńt�N�V�}���Ȃ��������̂悤�ɁA�������u�x�[�X���[�h�d���v�ƈʒu�Â��ĉғ��֓˂�������ł��܂��B
����̃G�R�E�X�g�[�u�Â����ʂ��A���炽�߂Č��݂Ɩ����̂���l���l����_�@�܂����B�i�瑺�j